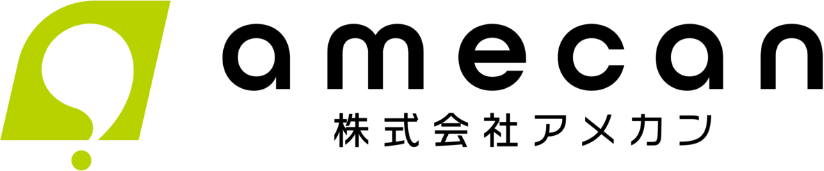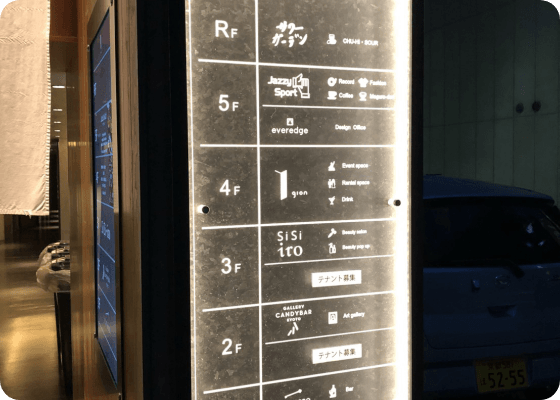【看板屋さん必見】京都市の看板、そんな簡単に付けたらあかんえ!?~番外編:暖簾の話編~ ⑪

【看板屋さん必見】京都市の看板、そんな簡単に付けたらあかんえ!?~番外編:暖簾の話編~
こんにちは〜!
**株式会社アメカンの「ameの方」**です☀️
今日は、あんまり“看板扱いされてへんけど看板やで”って存在。
暖簾(のれん)兄さんのお話です。
わい、暖簾です。…まだ現役で頑張ってます
生まれは室町。もう長老クラスやけど、
いまもなお、現場バリバリの営業担当やってます。
名前の由来は「“暖かさを連ねる”=暖簾」。
昔は寒さを防いだり、煙をさえぎったり、
いわば「ドアの代わりに垂れてた奴」やったんです。
「この店、営業中ですわ」って無言で伝える、無口な営業マンみたいな存在なんです。
看板とちゃうけど、看板以上の存在感出してます
たとえば和食屋さんで、
何にも看板ついてへんのに、
「スッ…」と暖簾が揺れてたら、それだけで営業中やってわかるやろ?
しかも、「店」って一発で伝わる。
ただそこにいてるだけで“店の雰囲気を伝える”力があるんです。
ま、聞いてってや
◎ メリットはこんなんや:
- 四季で色や素材を着替えられる(夏は麻、冬は綿)
→ ワイ、着回し上手やで。 - 外して洗えるし、管理もカンタン。
→ でも洗濯ネットは使ってね。わいデリケートやから。 - “動く看板”として、風でひらひら動くことで目を引ける。
△ デメリットはまぁ…正直あるで:
古くなったら端がほつれて、見た目“修行僧の袈裟”みたいになる。
雨の日はズブ濡れ。「びちょれん」って呼ばれる。
風が強いとバタバタして「この店、空いてんのか閉まってんのかわからん」ってなる。
それでもワイは、まだまだ現役やねん
最近の看板はLEDでピカピカ、アニメーションでグルグル、しゃべるやつまでおる。
「なんであんた、店より目立ってるねん」って言いたい時もあるで。
けどな、
ワイら暖簾は、“そっと空気に馴染む”看板や。
👘「あ、このお店、ちょっと寄ってみよかな」
ってお客さんに思わせる、“余白のチカラ”があるんや。
看板が「来い!」って叫ぶなら、
ワイは「よかったら…」って囁くんやで。
まとめ:ただぶら下がってるだけやない。“敷居と誘い”の気配の番人なんや
看板って、目立つために付けるもんや。
ほんで暖簾はな、ただぶら下がってるだけの布やないねん、
店と道行く人との“ちょうどええ境界線”の役目を受け持ってるんですわ。
お客さんの足を止めて、店の雰囲気を伝えて、
でも決して押しつけへん。風まかせで、品よく揺れて、
「あ、ここ入ってもええんかな」って思わせる、そんな存在なんやで。
というわけで今回は「あかんえ番外編・暖簾の話編」でした🌸
次回は「○○の話編」…光ってるのに“控えめ”ってどういうことやねん?って話、します。
株式会社アメカンの「ameの方」でした!
ご拝読ありがとうございました!
※ちなみに「canの方」は、祇園の割烹の暖簾を見て「…この布、風と一緒に時代も越えてきたんちゃう?」って言うてました。
なんかもう、“何をみても情緒を感じ感動する系”の人になってきてます。誰かたすけて(笑)